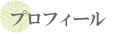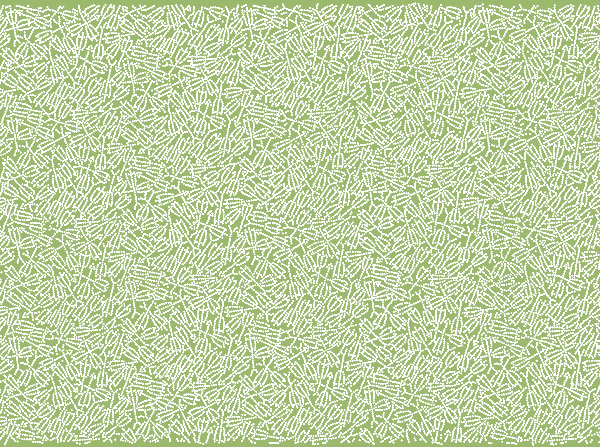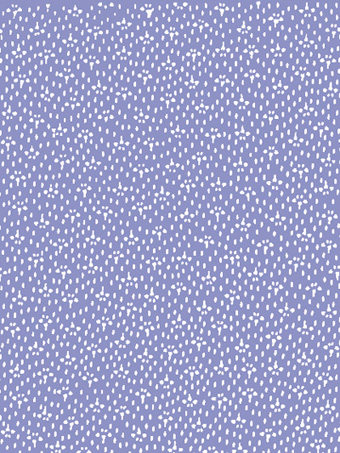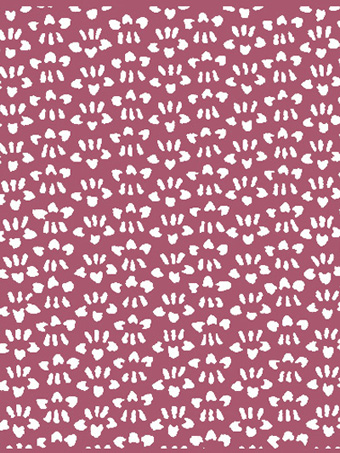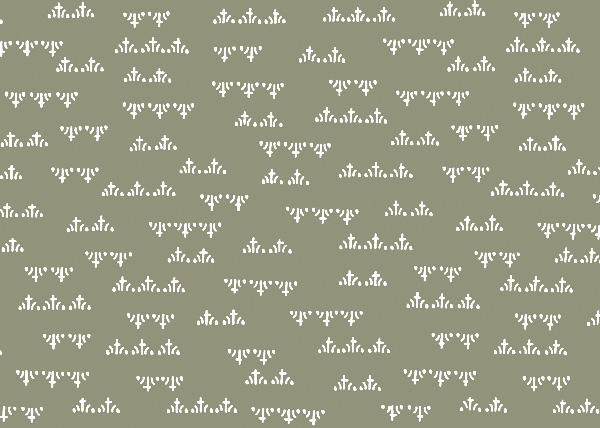|
端午の節句 菖蒲文様
我が家では端午の節句に、玄関の軒先に菖蒲の葉を挿します。
そして、親父が描いた魔除けの赤い鍾馗の内幟(うちのぼり)を飾り、薬効があるといわれる菖蒲湯に入ります。
孫たちは風呂で菖蒲の鉢巻きにするのを楽しみにしています。
32回の「桃の節句」でも書きましたが、端午の節句も江戸時代に定められた「五節句」の一つです。
元は中国から伝来した、病気や災難を祓う行事が起源だといわれ、
邪気を祓うとされる菖蒲やよもぎを体に当てたり、屋根や門に掛けたりしました。
菖蒲(しょうぶ)は尚武(武道や武勇を重んじること)と同じ読みをし、
さらに菖蒲の葉は堅く鋭い形なので、剣を想像させることから、端午の節句は男児の祝いの日となったといわれます。
子どもの誕生と成長を祝い、健康を祈る行事として一般に広まって来たようです。
五月人形の部屋飾りは兜や鎧、刀、武者人形、金太郎、弁慶などです。
室町時代から部屋飾りが豪華になったといわれていますが、
例えば、江戸日本橋の十件店(じゅっけんだな)の人形市は、4月25日から5月4日まで開かれ、
市場の人出はおびただしく、混雑は夜まで続いていたそうです。
懐中物を狙う盗人が多くいたことも市場の名物とか。
なにしろ、当時、ヨーロッパ最大の都市ロンドンが80万の人口だったのに比べ、
江戸は100万都市だったのですから、さもありなんです。
五月節句

5月5日の端午の節句に、七歳までの男児がいる家では、子どもたちが丈夫に育つよう、
その幸福を願って武者絵の幟旗(のぼりばた)を立てます。
この図は内幟(うちのぼり)という座敷飾りです。武者人形、太刀、鉾なども合わせて飾ります。
薬玉に檜扇

不浄を祓う薬玉は、魔除けのために端午の節句に飾ります。
平安時代には薬玉に香料や薬草を入れ、柱に掛けたり、腰に着けたりしていました。
江戸時代には、絹地の袋に花飾りや、五色の糸を垂らして見栄えの良い飾り物になりました。
檜扇は王朝趣味の文様として好まれた文様素材です。
鎧縅(よろいおどし)

鎧や札(さね)を組紐や革で綴ったものですが、この文様は男の子の衣装などに使い、
強く、凜々しくなってほしいと願って使われた文様でしょう。
矢羽根散らし
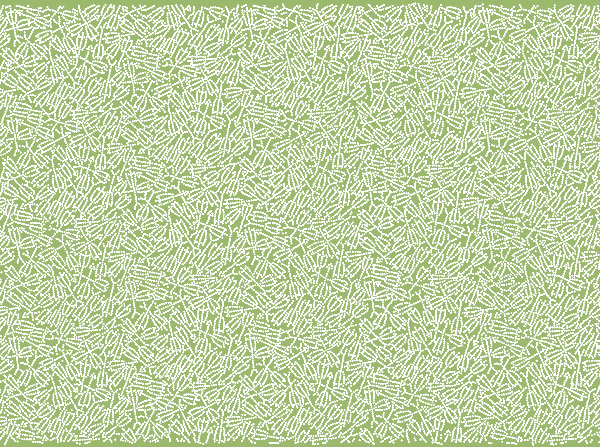
矢につける羽は威厳を持った鷹や鷲が最上級です。弓矢は剛の象徴として、祝い事などに供えられます。
この文様も男の子の衣装に好まれました。
粽(ちまき)

餅米や米粉などを笹で巻き、蒸したもの。元々は中国で作られた料理ですが、日本には平安時代に伝わってきました。
昔は茅(ち)の葉や、菖蒲の葉を使ったこともあったようです。今では端午の節句につきもののスイーツとなっています。
花菖蒲
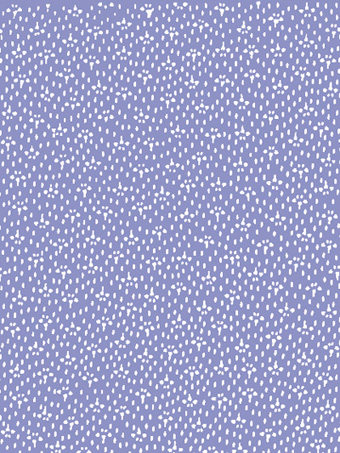 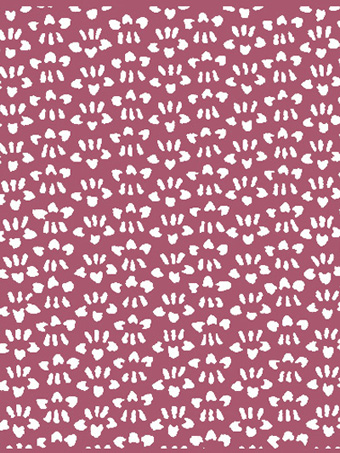
菖蒲には独特な香りがあり、虫除けになるところから、
魔除け、厄除けの印として端午の節句に軒先に挿したり、菖蒲湯にする習慣が伝えられています。
菖蒲はまた、初夏を代表する花でもあります。
菖蒲革(しょうぶがわ)
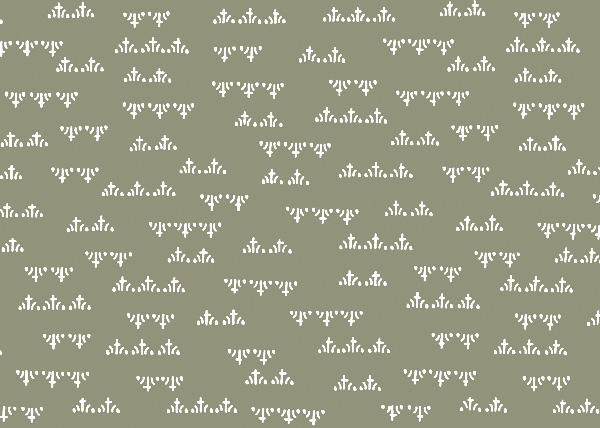
菖蒲は尚武、勝負に通じることや、葉の形が剣に似ているところから、武士に好まれました。
この文様は菖蒲を極端に意匠化した文様ですが、武具の染め革に盛んに使われています。
そのために「革」が文様名につけられました。
菖蒲革に鹿

神は鹿の姿で現れるともいわれ、鹿は神聖な動物とされています。
この文様はその鹿と菖蒲革の組み合わせです。戦国時代の武将は兜の前立にも鹿の角を使いました。
端午の節句に欠かせないものに「柏餅」があります。
柏の葉は大きく、古くは神棚に供える供物の器として使われていたことや、
柏の葉は新芽が育つまで古い葉を落とさないところから、
家系が絶えない、子孫繁栄にも関連づけて、縁起物とされたようです。
この頃には笹団子や、よもぎ餅など、香りの良い葉っぱで包んだ、懐かしい菓子が出回ります。
「風薫る五月」といいますが、私は食べ物から季節を感じることが多いようです。
01 May 2013
*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します
| バックナンバー |
| vol.040 | 貝文様 潮干狩り | 24 April 2013 |
| vol.039 | 向かい文様 江戸時代の恋愛観 | 17 April 2013 |
| vol.038 | 蝶 | 10 April 2013 |
| vol.037 | 霞か雲か | 03 April 2013 |
| vol.036 | 桜の花見 | 27 March 2013 |
| vol.035 | 「花」といえば桜 | 20 March 2013 |
| vol.034 | 春野 | 13 March 2013 |
| vol.033 | 蘭、四君子 | 06 March 2013 |
| vol.032 | 桃の節句 | 27 February 2013 |
| vol.031 | 天神様と梅 | 20 February 2013 |
| vol.030 | 梅 | 13 February 2013 |
| vol.029 | 竹 - 2 | 06 February 2013 |
| vol.028 | 竹 - 1 | 30 January 2013 |
| vol.027 | 鶴 | 23 January 2013 |
| vol.026 | 蓬莱山と松 | 16 January 2013 |
| vol.025 | 門松 | 09 January 2013 |
| vol.024 | 宝尽くし | 03 January 2013 |
| vol.023 | 留守文様 | 26 December 2012 |
| vol.022 | 雪 | 19 December 2012 |
| vol.021 | 悟り絵 | 12 December 2012 |
| vol.020 | 吹き寄せ | 05 December 2012 |
| vol.019 | 銀杏 | 28 November 2012 |
| vol.018 | 紅葉狩り | 21 November 2012 |
| vol.017 | 雀 | 14 November 2012 |
| vol.016 | 道具 | 07 November 2012 |
| vol.015 | 人物文様 | 31 October 2012 |
| vol.014 | 実りの秋 | 24 October 2012 |
| vol.013 | 雁 | 17 October 2012 |
| vol.012 | 草双紙と文具 | 10 October 2012 |
| vol.011 | 小紋-2 型地紙と型彫りの技法 | 03 October 2012 |
| vol.010 | 小紋-1 江戸小紋 | 26 September 2012 |
| vol.009 | 江戸のガーデニングブーム | 19 September 2012 |
| vol.008 | 重陽の節句 | 12 September 2012 |
| vol.007 | 船 | 05 September 2012 |
| vol.006 | 文字小紋 | 29 August 2012 |
| vol.005 | 蜻蛉(とんぼ) | 22 August 2012 |
| vol.004 | 団扇 | 15 August 2012 |
| vol.003 | 波文様五題 | 08 August 2012 |
| vol.002 | 『波紋集』 | 01 August 2012 |
| vol.001 | 梅鶴に松葉(うめづるにまつば) | 25 July 2012 |
|