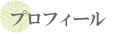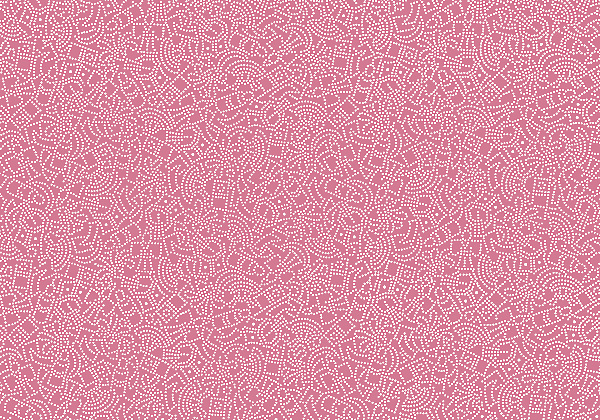|
桃の節句
五節句
旧暦の3月の初め、ひな祭りの頃を啓蟄といい、土の中の虫たちが春の陽気に誘われて動き出します。
桃もこの頃に咲き始めます。
3月3日はひな祭りですが、かつては「上巳(じょうし)の節句」といいました。
もとは中国の暦法で定められていた季節の変わり目のことですが、江戸時代に幕府が五つの祝日を定めました。
人日(じんじつ)の節句(1月7日)、上巳の節句(3月3日)、端午の節句(5月5日)、
七夕の節句(7月7日)、重陽の節句(9月9日)をそれぞれ式日と定め、
季節の節目に植物から命の力をいただき、身の穢れを祓う行事が行われました。
また、節句の日には季節にふさわしいものを食べる風習があり、
人日には七草粥、上巳には草餅やハマグリ、端午はちまきや柏餅、七夕はそうめん、重陽は栗飯を食べ菊酒を飲みます。
幕府が考え出した庶民へのご機嫌取りの定めであったかのも知れませんが、庶民はこれらの風習を大いに愉しんだようです。
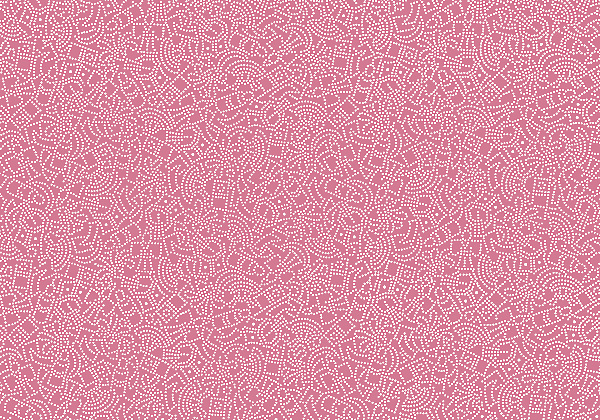
上巳の節句、ひな祭り
「ひな祭り」は本来、女の子の成長を願う風習で、
お雛様は子どもたちに降りかかる災難や厄を身代わりになって受け止めてくれる厄除けの守り神を意味します。
しかし、室町時代頃から貴族や武家の間で競って立派な雛人形を飾るようになり、
やがて江戸時代になると、武家や富裕な町人たちの間で一気に高価な雛飾りをするようになりました。
江戸時代の後期には2月25日頃から日本橋の十軒店(だな)、人形町、尾張町、麹町など、
何カ所にも「雛市」がたち、人形を買い求める客で賑わったといわれます。
幕府から華美を禁ずるお触れが再三出されるほどに、雛人形は大流行したようです。
ひな祭りは女性だけの祭りでしたので、菱餅や白酒をいただきながら、
人目を気にせずおしゃべりが愉しめて、一年一度の気晴らしが思う存分出来るという「晴れの日」でした。
紙折雛

3月3日の「上巳の節句」に、女児の居る家では紙人形を作り、子どもの体をさすり、病気や災いを祓います。
自分の身に降りかかる災難を代わりに引き受けた紙人形を川に流す「流し雛」がひな祭りの起源といわれますが、
このように呪術的な意味合いで平安時代頃から始まったといわれています。
犬張り子

この図は御伽犬(おとぎいぬ)、犬筥(いぬばこ)といい、
人面に似た犬をかたどった雌雄一対の張箱で、狛犬と同じ意味合いともいわれます。
犬は子どもを多く産むことから、守護、安産の守り神とされ、この犬張り子は桃の節句に雛壇に飾られます。
子どもの着物の模様としても用いられています。
三方菱の餅

三方は神仏に供え物を奉り載せる檜の台です。方形の折敷(縁つきの盆)で
前、左右の三方に刳(く)り形(くってあけた穴)があります。
菱餅は雛の節句の供物で紅、白、緑の三色を重ねた菱形の餅です。
紅は先祖を尊び厄を祓い、桃の花を表します。
白は清浄で雪を表し、緑は草餅ですが、大地から芽生える命の力を表します。
このように菱餅は花、雪、大地のエネルギーをいただこうというありがたいお餅なのです。
子どもを思う親心から生まれ、季節の色を取り入れた色合いでしょう。
葉付き桃

桃は中国原産といわれますが、日本では弥生時代の遺跡から桃の種が大量に発見されています。
中国では桃は「西王母」といわれます。
仙女である西王母の庭の桃は、三千年に一度実を付け、これを食べると寿命が延びるとされます。
漢の武帝が長寿を願っていた際、西王母は天から下り、仙桃七顆を与えたといわれ、
中国では正月飾りの「年画」には必ず桃の実の絵が描かれています。
そして、桃文様は延命長寿の吉祥文様として日本に伝わってきたものです。
ひな祭りが近づくと、花売りは荷籠に桃の花など、春の花をいっぱいに入れ
「花イ、花イ」と呼びながら、花鋏をチョン、チョン鳴らして売り歩きました。
27 February 2013
*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します
| バックナンバー |
| vol.031 | 天神様と梅 | 20 February 2013 |
| vol.030 | 梅 | 13 February 2013 |
| vol.029 | 竹 - 2 | 06 February 2013 |
| vol.028 | 竹 - 1 | 30 January 2013 |
| vol.027 | 鶴 | 23 January 2013 |
| vol.026 | 蓬莱山と松 | 16 January 2013 |
| vol.025 | 門松 | 09 January 2013 |
| vol.024 | 宝尽くし | 03 January 2013 |
| vol.023 | 留守文様 | 26 December 2012 |
| vol.022 | 雪 | 19 December 2012 |
| vol.021 | 悟り絵 | 12 December 2012 |
| vol.020 | 吹き寄せ | 05 December 2012 |
| vol.019 | 銀杏 | 28 November 2012 |
| vol.018 | 紅葉狩り | 21 November 2012 |
| vol.017 | 雀 | 14 November 2012 |
| vol.016 | 道具 | 07 November 2012 |
| vol.015 | 人物文様 | 31 October 2012 |
| vol.014 | 実りの秋 | 24 October 2012 |
| vol.013 | 雁 | 17 October 2012 |
| vol.012 | 草双紙と文具 | 10 October 2012 |
| vol.011 | 小紋-2 型地紙と型彫りの技法 | 03 October 2012 |
| vol.010 | 小紋-1 江戸小紋 | 26 September 2012 |
| vol.009 | 江戸のガーデニングブーム | 19 September 2012 |
| vol.008 | 重陽の節句 | 12 September 2012 |
| vol.007 | 船 | 05 September 2012 |
| vol.006 | 文字小紋 | 29 August 2012 |
| vol.005 | 蜻蛉(とんぼ) | 22 August 2012 |
| vol.004 | 団扇 | 15 August 2012 |
| vol.003 | 波文様五題 | 08 August 2012 |
| vol.002 | 『波紋集』 | 01 August 2012 |
| vol.001 | 梅鶴に松葉(うめづるにまつば) | 25 July 2012 |
|