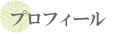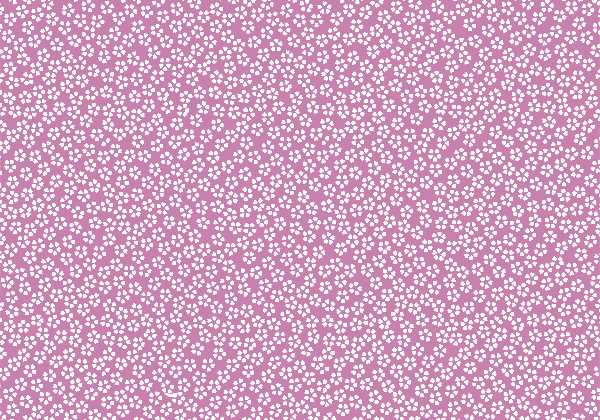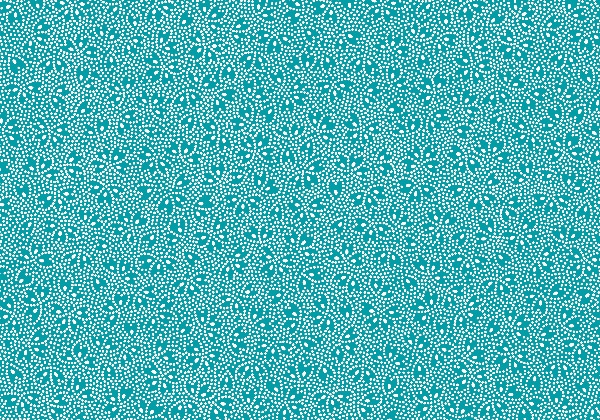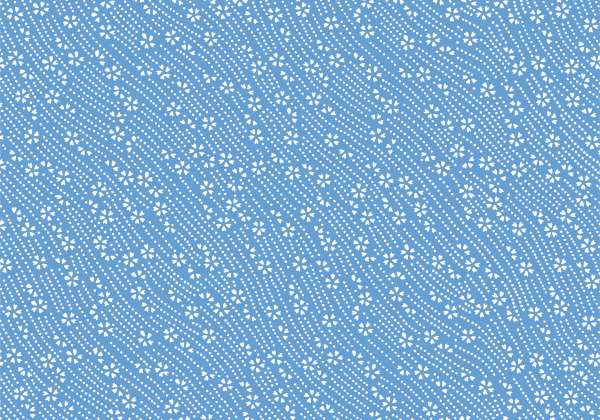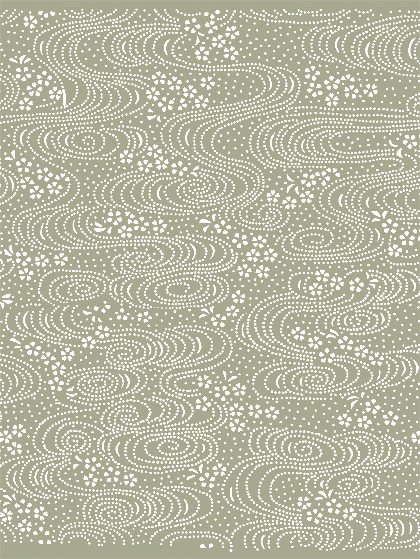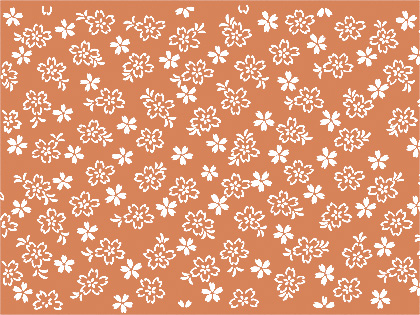|
「花」といえば桜
奈良時代には「花」といえば「梅」の花でしたが、
平安時代になり桜が貴族に愛されるようになると、一気に花の代表は桜に替わってしまいました。
現代では、日本中どこでも校門の近くには桜が植えられています。
ちょうど入学式の頃に満開になるので、新入生歓迎の意味を込めて植えられたのでしょう。
最近では、オリンピック招致のシンボルマークに桜が使われ、桜は日本を代表する花として海外にアピールされています。
NHK大河ドラマ『八重の桜』では、「桜」が福島復興のシンボルとして扱われていますが、
江戸時代は、どちらかといえば桜は散り際の見事さから武士に愛され、
「滅びの美」として大衆の心情にもぴったりのようでした。
能の世界では桜が「雅や幽玄」「無情」「悲しみ」の象徴として扱われることが多くあります。
同じ花でも、込められる意味合いが様々に変わっていくようです。桜ほど日本人の美意識に影響を与えた花はないでしょう。
平安時代の歌人、西行は
「ねがはくは花のしたにて春死なむそのきさらぎの望月(もちづき)のころ」という歌を残しています。
小桜
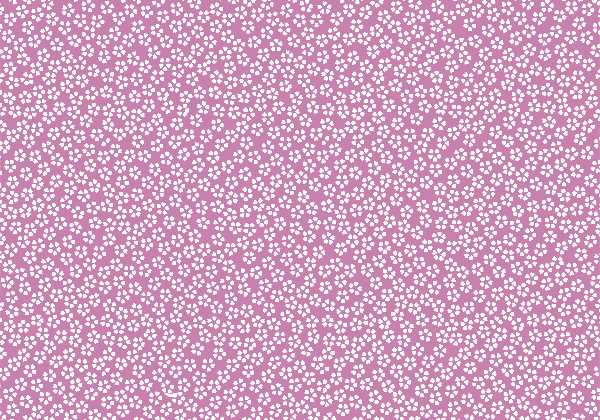
桜は『古事記』や『日本書紀』にも見られ、古くから日本人に愛された花です。
この図は花の代表として小さな桜花を一面に散らした、最も代表的な桜小紋柄で、
季節を問わず華やぎを表す文様として使用されています。
桜
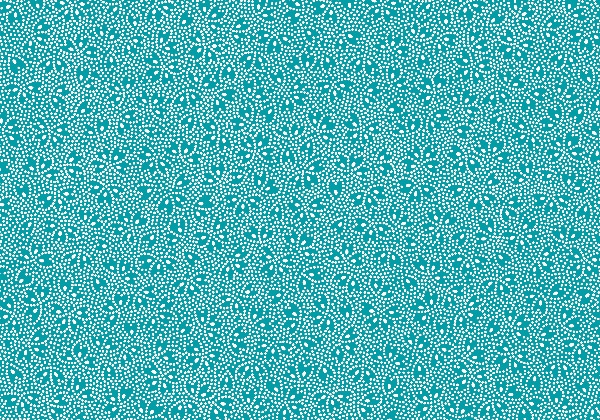
桜文様は大衆に有卦が良く、文様の作り手としては腕のふるいどころです。
この柄の着物は通りすがりに見たのでは何の文様かわかりませんが、近くでじっくり見れば桜の花びらの散らし文様。
そこから二人の話が弾みそうです。
吉野川
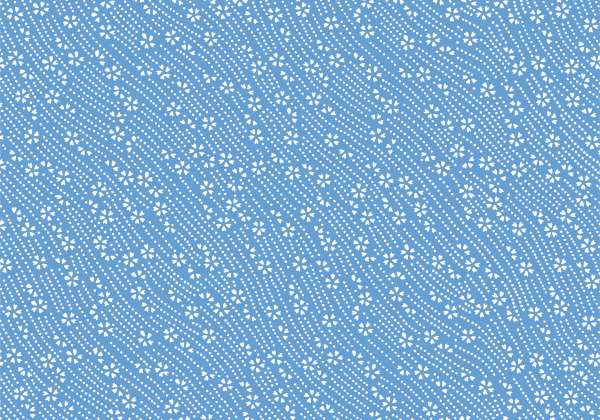

西行の歌と秀吉の「吉野の花見」により、日本の桜の名所は吉野となりました。
川の流れと桜の組み合わせ文様は吉野川の川面を流れる桜のイメージで、「吉野川」と定まっていました。
一瞬にして散ってしまった桜の花びらが川面を流れる様子を惜しみ、文様にしたのでしょう。
でも、吉野まで旅することは容易なことではありません。
せめて文様の名前に名所を入れ込んで、少しでも旅をした気分を味わいたいと思ったのでしょう。
花筏(はないかだ)
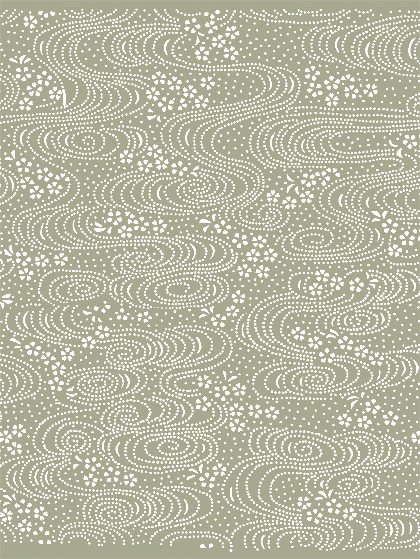

ハラハラと舞い落ちる無数の花びらは、川のよどみに集まり、やがて大きな渦をなして流れます。
この様を「筏流し」に見立てた、優雅なネーミングです。
花びらは花見のざわめきの余韻を残して、いつまでも沈まないでほしいという願いを筏に託して川面を流れていきます。
下図は京都、高台寺蒔絵で有名な絵柄を参考にしたとように見えます。
花散らし
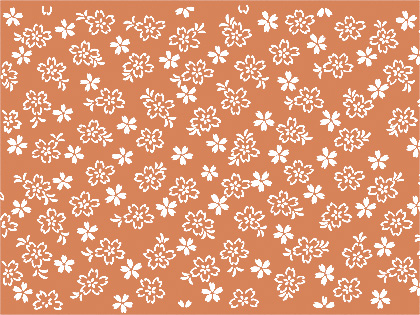
「桜花(おうか)文様」ともいいます。満開の桜をイメージさせる文様です。
琴柱桜

「琴柱」とは、琴の弦を支える器具です。この図は、琴柱のおもしろさを強調し、そして桜と組み合わせたものです。
今を盛りと咲き誇る桜の下での花見の宴、琴の音の響きを連想させる、華やかな表現となっています。
琴柱は形のおもしろさからたびたび使われる文様資材です。
江戸時代の屏風絵を見ると桜の木の下で、幔幕を張り宴会をしている様子が描かれています。
次回は待ちに待った「花見」です。
20 March 2013
*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します
| バックナンバー |
| vol.034 | 春野 | 13 March 2013 |
| vol.033 | 蘭、四君子 | 06 March 2013 |
| vol.032 | 桃の節句 | 27 February 2013 |
| vol.031 | 天神様と梅 | 20 February 2013 |
| vol.030 | 梅 | 13 February 2013 |
| vol.029 | 竹 - 2 | 06 February 2013 |
| vol.028 | 竹 - 1 | 30 January 2013 |
| vol.027 | 鶴 | 23 January 2013 |
| vol.026 | 蓬莱山と松 | 16 January 2013 |
| vol.025 | 門松 | 09 January 2013 |
| vol.024 | 宝尽くし | 03 January 2013 |
| vol.023 | 留守文様 | 26 December 2012 |
| vol.022 | 雪 | 19 December 2012 |
| vol.021 | 悟り絵 | 12 December 2012 |
| vol.020 | 吹き寄せ | 05 December 2012 |
| vol.019 | 銀杏 | 28 November 2012 |
| vol.018 | 紅葉狩り | 21 November 2012 |
| vol.017 | 雀 | 14 November 2012 |
| vol.016 | 道具 | 07 November 2012 |
| vol.015 | 人物文様 | 31 October 2012 |
| vol.014 | 実りの秋 | 24 October 2012 |
| vol.013 | 雁 | 17 October 2012 |
| vol.012 | 草双紙と文具 | 10 October 2012 |
| vol.011 | 小紋-2 型地紙と型彫りの技法 | 03 October 2012 |
| vol.010 | 小紋-1 江戸小紋 | 26 September 2012 |
| vol.009 | 江戸のガーデニングブーム | 19 September 2012 |
| vol.008 | 重陽の節句 | 12 September 2012 |
| vol.007 | 船 | 05 September 2012 |
| vol.006 | 文字小紋 | 29 August 2012 |
| vol.005 | 蜻蛉(とんぼ) | 22 August 2012 |
| vol.004 | 団扇 | 15 August 2012 |
| vol.003 | 波文様五題 | 08 August 2012 |
| vol.002 | 『波紋集』 | 01 August 2012 |
| vol.001 | 梅鶴に松葉(うめづるにまつば) | 25 July 2012 |
|