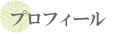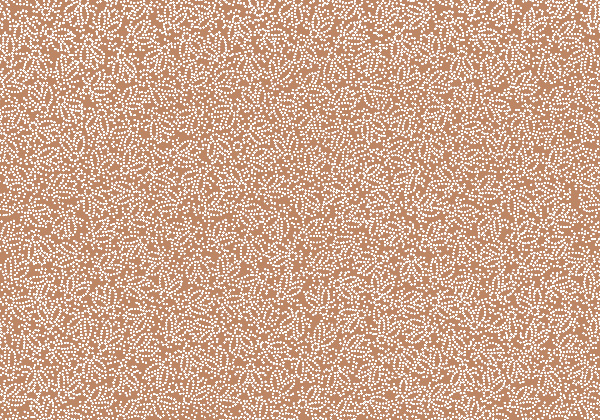|
春野
啓蟄も過ぎ、うららかな陽気に誘われて人々は野山に出て若菜摘みをします。
江戸時代は女性が遊びで外出することはほとんどできなかったので、若菜摘みや桜の花見などは数少ない楽しみでした。
若菜摘みで人気があったのは嫁菜(ヨメナ)です。菊科の多年草で、免疫力を高めるビタミンCが多く含まれています。
他にも肌の若さを保ったり、体に良いカテキンなども含まれているそうです。
若菜に薄衣をつけて揚げ物に、おひたし、胡麻和え、油炒め、嫁菜飯などなど、愉しめます。
薬草は身の穢れを祓い、無病息災を願います。こうした薬草摘みは、ひな祭りの起源ともいわれています。
日当たりの良い緩やかな南斜面は絶好の草摘み場所です。
江戸では向島、新宿の十二社(じゅうにそう)、亀戸、道灌山、日暮里などが有名でした。
今では想像ができませんが江戸といっても少し歩けば自然がいっぱいでした。
春野

うららかな春の野原に草摘みに出かけるのは女性にとっては数少ない外出の楽しみです。
日差しを避けるため、娘さんたちは菅笠をかぶり、花摘みや病封じの薬草採りを愉しみました。
この文様はわざと女性の姿を入れないことで、見る人たちにその場の雰囲気を想像して愉しんでもらおうという構成です。
蒲公英(タンポポ)

「春野」の文様にも菅笠の下にタンポポの葉が見えています。
第21回の悟り絵文様にも書きましたが、タンポポは「鼓草」とも呼ばれていました。
江戸時代の名産品などを集めた「毛吹草(けふきぐさ)」という本に書かれています。
タンポポの根は非常に強くなかなか切れないので、鼓の音「根」が強く切れないとうにという意味合いが込められた名称です。
鼓の胴には蒲公英模様の蒔絵が時々見かけられます。
蒲公英は日本油菜ともいいますが、葉や根は薬になるそうです。
菫

「春野にすみれ摘みにと来し我ぞ野をなつかしみ一夜寝にける」(山部赤人)と
『万葉集』にも詠われる春野の代表のような可憐な姿は特に女性好みです。
なにしろ宝塚歌劇団を象徴する歌のトップに出てくるのですから。
スミレ色というと紫色が思い浮かびますが、日本には百種類以上の菫があり、色合いも様々にあるようです。
山菜としても利用されたようです。葉は天ぷらや、おひたしや和え物になります。花は酢の物に使えます。
土筆

古くはツクヅクシと呼ばれ『源氏物語』にも出てきます。
地面から頭を出し、その形が筆に似ているところからこの名称が生まれました。
ほのぼのとした春の風物詩的な文様です。土筆ももちろん食べられます。
笹に蕨

どこの里山でも、日本中どこでも見かけられる、のどかな早春の田園風景文様です。
笹は冬の寒さや雪に耐え、土の中からは蕨が顔を出します。
蕨の先端は子どもの手招きにも見え、熨斗の形に似ているので早蕨だけを文様にした「熨斗文様」が生まれました。
(熨斗文様については、いずれ詳しく書きます)
蜂
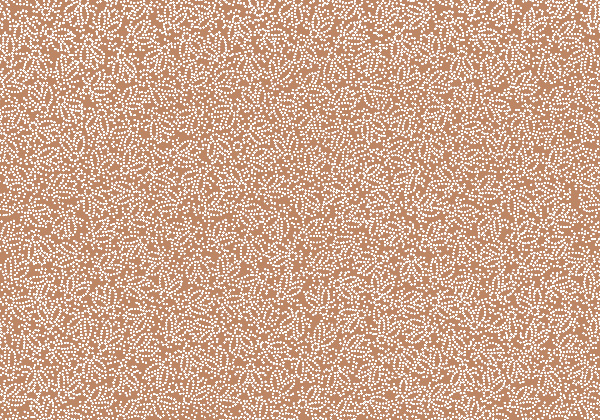
春の花が咲き誇ると蜂や蝶が大活躍です。
世界的に養蜂の歴史は古くエジプトの古代遺跡からも壺に入った蜂蜜が発見されたといわれます。
日本でも奈良時代には大和の三輪山で放養した記録があります。
そして江戸時代には巣箱を用いた養蜂が始まったといわれます。
働き蜂の文様は収穫を意味し、有卦の良い文様です。
さらに、ここでも語呂合わせで、ハチを末広がりの「八」に重ねて縁起の良い文様となります。
江戸の人たちは語呂合わせや、駄洒落が大好き!
早春の野原は土からの生命力を直接、体で感じることができ、
私の年になると特に植物の芽吹き(命富貴)にあやかりたい気持ちになります。
ここらで腰を上げ、早春の穏やかな日射しに誘われて、近くの川辺に散歩に出かけましょうか…。
13 March 2013
*このページに掲載されたコンテンツは熊谷博人に帰属します
| バックナンバー |
| vol.033 | 蘭、四君子 | 06 March 2013 |
| vol.032 | 桃の節句 | 27 February 2013 |
| vol.031 | 天神様と梅 | 20 February 2013 |
| vol.030 | 梅 | 13 February 2013 |
| vol.029 | 竹 - 2 | 06 February 2013 |
| vol.028 | 竹 - 1 | 30 January 2013 |
| vol.027 | 鶴 | 23 January 2013 |
| vol.026 | 蓬莱山と松 | 16 January 2013 |
| vol.025 | 門松 | 09 January 2013 |
| vol.024 | 宝尽くし | 03 January 2013 |
| vol.023 | 留守文様 | 26 December 2012 |
| vol.022 | 雪 | 19 December 2012 |
| vol.021 | 悟り絵 | 12 December 2012 |
| vol.020 | 吹き寄せ | 05 December 2012 |
| vol.019 | 銀杏 | 28 November 2012 |
| vol.018 | 紅葉狩り | 21 November 2012 |
| vol.017 | 雀 | 14 November 2012 |
| vol.016 | 道具 | 07 November 2012 |
| vol.015 | 人物文様 | 31 October 2012 |
| vol.014 | 実りの秋 | 24 October 2012 |
| vol.013 | 雁 | 17 October 2012 |
| vol.012 | 草双紙と文具 | 10 October 2012 |
| vol.011 | 小紋-2 型地紙と型彫りの技法 | 03 October 2012 |
| vol.010 | 小紋-1 江戸小紋 | 26 September 2012 |
| vol.009 | 江戸のガーデニングブーム | 19 September 2012 |
| vol.008 | 重陽の節句 | 12 September 2012 |
| vol.007 | 船 | 05 September 2012 |
| vol.006 | 文字小紋 | 29 August 2012 |
| vol.005 | 蜻蛉(とんぼ) | 22 August 2012 |
| vol.004 | 団扇 | 15 August 2012 |
| vol.003 | 波文様五題 | 08 August 2012 |
| vol.002 | 『波紋集』 | 01 August 2012 |
| vol.001 | 梅鶴に松葉(うめづるにまつば) | 25 July 2012 |
|